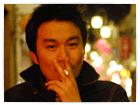Ingwer Design
Staff Report
ingwer design report 「山口也寸志の閉ざされた手帳」
枕元に積み上げられた本の壁。猫と本と也寸志。閉ざされた手帳の中身は・・・。どうぞお見逃しなく。
俺っちなんかこういい気分なんだよな
2006.2.26[Sun]
今まで読まず嫌いだった作家や敬遠してきた小説家、そんな人を読んでみようと書店に行った。そこで目にとまったのが村上春樹の「海辺のカフカ」だった。
中学のとき僕は村上春樹が好きだった。ノルウェーの森を読み、風の歌を聴け、羊をめぐる冒険、ダンスダンスダンスと立て続けに読み感銘を受けた記憶がある。しかし高校に入ってからあまり読まなくなり、「スプートニクの恋人」が出た際に久しぶりに読もうと思って手にとったときなどは最初の数ページで嫌悪感を抱いたものである。だから今回は十数年ぶりの村上春樹なのである。
ゆっくり読み進め、数日前に読み終わってみると、、、それはとてもおもしろい本だった。15歳の少年カフカが“世界で一番タフ”になるために必要なことを感じ、経験し、成長していく姿を“メタファー”を大切にしながらも、風景描写や人物の行動などの細部をおろそかにせず力強く丁寧に描いて、有意義な時間を過ごさせてくれた。好き嫌いはあるかも知れないが、今これだけパワーのある小説家は決して多くはないと思う。
彼は巧みなストーリーテリングで読者をあきさせずに、登場人物がそれぞれに持つ欠落、小さい、大きい欠落、孤独感、くだらないことだけど誰もが感じたことのある恋愛の気持ちなどを、独自の文体(それが嫌悪感の原因だと思うけど)で、ベタベタせず、真摯に描いている。それが出す小説出す小説がベストセラーになる村上春樹の理由のひとつかもしれない。ようするに人はみな孤独なのである。そして登場人物の迷い、矛盾、弱さなども多くの共感を得ているところだろうが、それとあわせて人物の芯の強さ、ストイックさも、自分ができないことをしてくれるものとして、憧れの対象として、多くの読者の共感を得ているのではないだろうか。もちろんいわゆるヒーローは出てこない。しかし例えば物語の重要な核である佐伯さんの、本当に大切なものを知ることができ、その大切なものをなくしたとき、本当の意味でそれを忘れず、傷を開いたまま、自分を貶めながら生きていく生き方は、陳腐で単純なことだけど、事実そのように生きていくことは崇高なことである。そしてそれを理解してプラスに変えて生きていってくれる少年に想いを引き継ぐことができることは幸せなことである。人はそのような人に憧れを持つものだ。ようするに思った通りに生きられない人が多いのだ。もちろん「痛みというのは個別的なもので、そのあとには個別的な傷口が残る」とこの小説の中にあるように、感じ方は十人十色であるし、そうでなければならいのだけれど、人が感じる最大公約数的な寂しさみたいなものを掬い上げるのが上手い人なのだろう。(もうひとつうがった見方をすると、彼の小説はどことなく外国の小説のような雰囲気がある。ベストセラーになる背景には、日本人のそんな外国への憧れもあるのかも知れない、なんて思ったりもした。)
そして何よりこの小説で一番の収穫は”ナカタさん”である。この人が本当にいい。村上春樹が作った最も魅力あるキャラクターではないだろうか。
あることをきっかけに文字を読むことが出来なくなり、知的障害を持ったナカタさん。猫と話が出来るおじさんであるナカタさん。一緒に旅をする星野青年が「ナカタさんの横にいると〜俺っちなんかこういい気分なんだよな」と言うとおり共にいるだけで満たされていくのだろうと思える人である。ゆっくりと自分のやるべきことをこなしながら、「きわめて限定された語彙の中で」生きているナカタさんは、周りから見れば充足して、僕らが忘れた大切なことを守りながら、それなりに幸せに生きているように思える。グレートギャツビーにある「人生は結局のところひとつの窓から見たほうがよく見えるのである」ということを感じさせてくれもする。しかしそれは半分正しくて半分間違っているのであろう。
なぜなら小説の初めでは「すべてのなかに身を浸すことが何にも増してありがたい」と話していたナカタさんは、自分の使命に気付き本当に生き始めると「ナカタには逆らえるだけの力がありませんでした。なぜならばナカタには中身というものがないからです。」と空っぽの自分に悩み、文字を読むことができないことを嘆くのだから。そしてそれは本当に生き始めた人すべてが感じることなのではないだろうか。自分の無力を感じれない人のことを僕は信じられない。
ナカタさんと出会えただけで、僕はこの小説を読んだ甲斐があった。
村上春樹に対して僕の持っていた嫌悪感。それはさっきも書いたけれど、その文体にあった。しかし理由は分からないが、なぜか今回はあまり気にならなかった。僕の心が広くなったのか。そんなことはありえない。15歳のころの感覚にもどったのか。それもありえない。なぜだか理由は藪の中である。しかしあまり気にならなかっただけで、全くなくなった訳ではないのだ。やはり登場人物に「やれやれ」とかつぶやかせたり、「手のひらの感触を、なにかの思想みたいにペニスのまわりに感じる」とかの表現に僕はイライラした。思想って言われても。。。星野青年が風俗嬢とプレー中に哲学の話をするシーンも同様である。そういえば大西巨人が大江健三郎の小説の中の似たようなシーンを取り上げ、SEX中にそういったことを考えるのは決して上等な行為ではないと批判していた。ロラン・バルトは“テクストの快楽“の中で「愛するものと一緒にいて別のことを考える。するといちばんいい考えが浮かぶ」と書いていたが、バルトは恋愛のことは疎そうなので、やはり大西巨人に軍配が上がるだろう。そしてカフカというネーミングもそうである。少年にカフカってつけるセンスがなぜか僕をいらだたせたのも事実だ。そしてこれもまた大江さんのある小説の中でジブラルタルという名の猫が出てくるのだが、これに対してたぶん平野謙だったと思うが、猫にジブラルタルという名をつけるセンスを批判していた。僕と同じようにイライラしたようである。僕は大江健三郎は大好きである。一番好きと言ってもいい。そうなるとこういったことは単に好き嫌いの問題かも知れないけれど。。。しかし村上春樹と大江健三郎。全くタイプは違うのに、そういったところのセンスには妙な符合があるような気がしないでもない。関係ないが古井由吉がその影響力の大きさということで二人を比べていたことがある。大江さんの場合は影響されるが反発の要素も含んでいるが (武満徹も大江さんの小説を読者の想像力の入りこむ余白があると言っていた。)、村上春樹の場合は完全に染まってしまう人が多いのではないかと。
ともあれ「海辺のカフカ」はよい小説である。海外での評価が高まっていることに、僕達はもっと誇りをもっていいのかも知れない。
最後に村上春樹の小説は攻撃的である。その雰囲気に騙されてはいけない。そして「海辺のカフカ」は政治小説としても読めると思う。彼は現実との手は離さないのだ。それは小説家としてとても尊敬できることであると思う。

微熱
2006.2.10[Fri]
今日の帰りの電車の中、”辻”を読み終えた。古井由吉の新刊連作短篇集だ。
古井さんは長く僕の好きな作家である。耳を澄ませて書き取るその文章は、それだけで小説を読む悦びを教えてくれる。
辻とは、いくつかの道が交差するところであり、分かれ道である。
「人は一つの辻を通り越して、また次の辻に差しかかる。思い出すと、どうもそこで自分の運命が分かれたらしい。だが、現在もまだ自分が同じ辻をたどっているようでもある。そういう辻が、おそらく無数にあるだろうと思いました」と古井さんは”MSN-Mainichi INTERACTIVE”のインタビューで答えていた。
僕は”辻”をちゃんと渡って来ただろうか。
いつも古井さんは日常の中で繰り返される行為から生まれるズレと、そのズレを豊かな感受性ゆえに抱えて狂っていく人を描いてきた。ほんの些細な狂いもあれば、人生を包む狂いもある。
特に昨今は壮年から老年の生きることと死ぬことの、日常の生活で生まれる境を、特有の濃密な文章で、時に幽玄に、時にリアルに、そして時に幽玄がリアルに、リアルが夢につながるように、描いてきた。
この連作も基調はそれと同じものだが、今回は特に男女の心の動きと性を大きく扱っているためか、その世界は”米粥の濃厚な臭い”のする生々しささえ感じさせ、時に疎ましくも思えるものだった。
しかし遠い記憶、気付いていない傷、夢、些細な振る舞い、日々の生活の所作などが生む、心と身体の狂いと矛盾を、禅問答のように、夢のように、独特の深い文章で書き連ねていくときに、イライラしながらも、結果それは生きることに寄り添ったものと納得させられていくのだ。
繰り返される既知が、ふっと未知になるとき。知らないはずのものが、もうずっと昔から知っているような気がするとき。自分の中でしか知れない些細なことが、それなしでは生きていけないような、歪みを、狂いを抱えていく。
しかしそこでは見えていて見えないとか、聞こえていて聞こえないといったことは、健康で幸せな人の言うことではないのかという疑問も生まれる。見えない人には見えないものは見えないし、聞こえない人には聞こえないものは聞こえないのだと。しかし狂いとは得てして、一見そんな幸せそうな人をこそ襲うものなのかも知れない。
それぞれに、その人なりの、想いの重さがあるのだと。それぞれが無数の”辻”を渡り、これからも差しかかるのだと。そしてそんな想いは普通他の人には伝わらず、ただあいつは弱いの一言で終わってしまうものだろう。
しかし古井由吉は違う。執拗にその人の声と環境に耳を澄まして、肯定も否定もせず、差し出してくれるのだ。
(勝手な想像だけれど、彼がそれをするのは彼が死の声を聞いたことがあり、見たことがあるからなのではないか)
人の脆さと合わさった豊穣さは、差異と反復の切なさは、個々の短篇のテーマでありながら、最近の別々の連作小説集全体でも形成されている。それは”人間喜劇”のように、全体でひとつの大きな長編小説なのではないだろうか。
柄谷行人は古井さんの文章を梶井基次郎とあわせて、彼の小説は微熱をもっていると書いていた。なるほど彼の小説が瑞々しいのはそのためだったのだ。
微熱を持つことは、若さの証拠なのだから。
いくら歳を重ねても、古井由吉は若いのだ。
「ここは、誰にも見えないが、辻なのだ、と言った。四方から道が集まってここで消える、出て行くと見えるのは、見せかけに過ぎない、人もここに差しかかっては失せる、それでも繰り返し差しかかる、先へ先へ惹かれて熱心にやって来る、もう済んでいるのも知らずに」
(半日の花 より)
読み終わってしばらくは、僕は古井由吉の目で物事を見ていた。そんな文体を持った小説家は、ほんの数人しかいない。

知ったことか
2006.2.4[Sat]

ここ数年、僕は年末年始にミステリをまとめて読む。
”このミステリがすごい”や”本格ミステリ””週刊文春”などがその年のベスト10を発表するためだ。
必ずしもそのランキングから選ぶわけでもないのだが、僕はミステリは好きなくせに、今まであまり読んではいず詳しくないため、それらは選択の目安となって助かるのである。
で今年これまでに読んだものは、「容疑者Xの献身/東野圭吾」「骨と髪/レオ・ブルース」「輝く断片/シオドア・スタージョン」「クライム・マシン/ジャック・リッチー」「愚か者の祈り/ヒラリー・ウォー」「失踪当時の服装は/ヒラリー・ウォー」「柔らかな頬/桐野夏生」。
まず○×△で僕の感想を書こう。
容疑者Xの献身 ×
骨と髪 △
輝く断片 △
クライム・マシン ○
愚か者の祈り △プラス
失踪当時の服装は △
柔らかな頬 ○
かつて僕はミステリ好きの少女に、あなたの感想は小難しくてうざったいと言われたことがあるのだが、○のものについてなら書いても構わないだろう。
クライム・マシン
気の利いたストーリーと軽やかなどんでん返しが楽しいミステリを集めた短編集である。ちょっとコーエン兄弟の映画にも似ていて(時代的にはコーエン兄弟が似ているというべきなのだが。)、読んでいてニヤっとされられながら、心楽しい時間を過ごさせてくれた。
いい意味で最高の時間つぶしである。
自分でも理由は分からないが、何故か僕はミステリの短編に対して高を括っていたところがあり、それをきれいに裏切ってくれたミステリだった。この作者、もっと他のものも読みたい。
柔らかな頬
桐野夏生の直木賞受賞作である本作は、単なるミステリに収まらない力作である。単行本の発刊からもうだいぶ時はたっており、文庫化してからも数年たっているので、なにをいまさらといった感は否めないが、ともあれよかった。
内容は失踪した娘探しのドラマなのだけれど、昨今流行の安易なトラウマ物にはない厳しさがある。
納得できないことを納得しないままに生きることの強さと残酷さ、終わりを見つけることの難しさ。それらを力強く描いている。主人公のカスミは自分勝手で、自己正当化を繰り返し、周りを傷つけている女性である。全くカスミは腹立たしい女性である。僕も読んでいて何度もそう思った。
しかし傷は癒さなければ生きていけないのに、そして傷を癒さないことは自分だけではなく、周りもさらに傷つけていくのに、それを自ら開いたままにする感受性に僕は感嘆する。
結果現実の生活でも精神面でもカスミは落ちていくだろう。きっと社会からはどうしようもないやつだと言われるだろう。そしてその再生も誰にも気付かれることはないだろう。
しかしそんなことは知ったことか。誰にも忘れられて、省みられないことを小説は伝えるのであるから。そんなことを、そんな人を、小説家が書かないで誰が書くのだ。
発刊当時から僕はこの作品のことは知っていたけれど、何故か読まなかった。その時にこれを読み、犯人は誰なのか、カスミのことをどう思うかなど、いろいろと話したかった。